意志のモダリティ
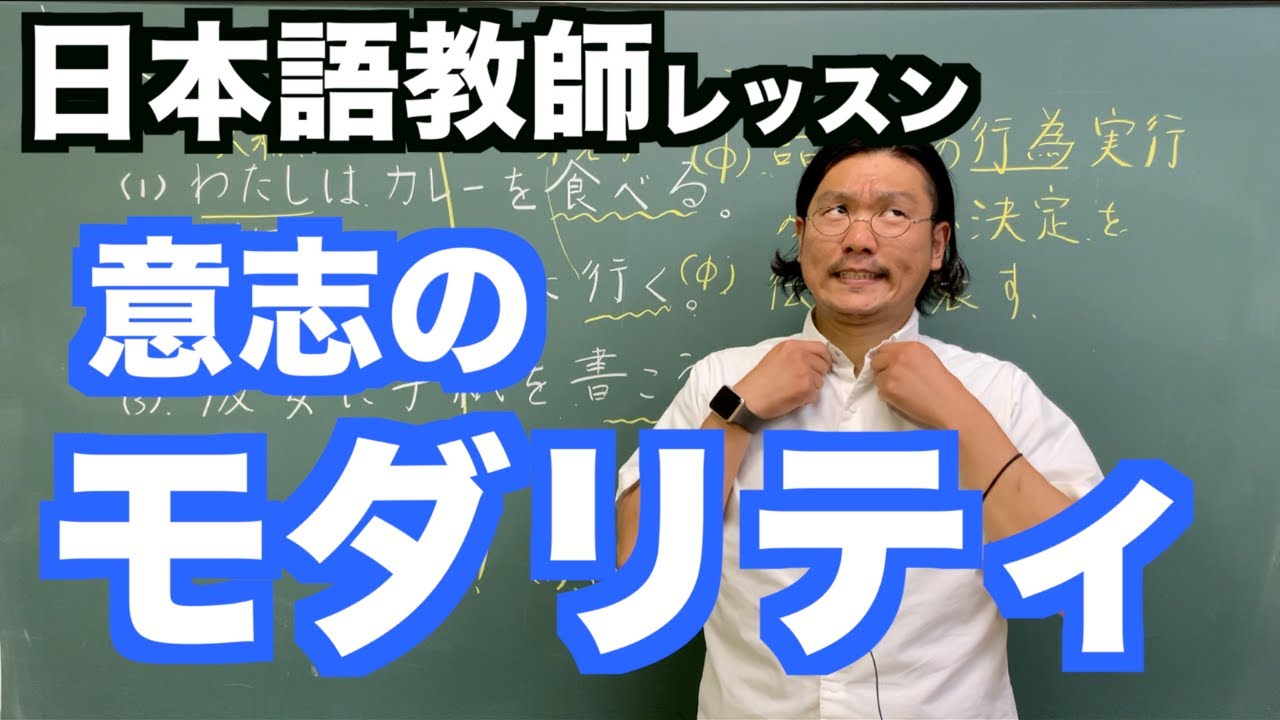
Other languages can be selected from the menu bar
・モダリティ kosendayuji
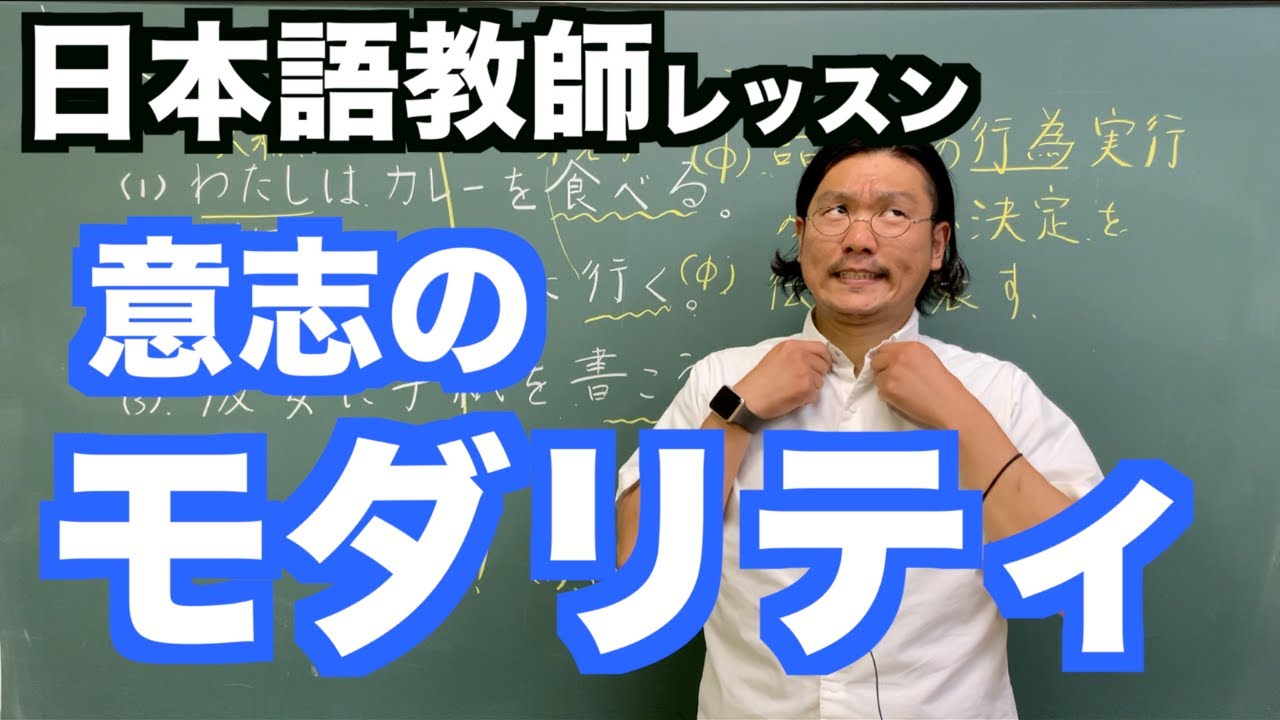
このページでは意志のモダリティについて学びましょう!
こう見ると紛らわしいですよね……でも大丈夫!
実際に例を見ながら考えていきましょう!
赤本(参考書)などでは、断定のモダリティと同じような書き方で意志のモダリティは説明されることが多いです。違いをしっかり押さえましょう。
この「食べる」は一見、断定のモダリティのように見えますが、意志のモダリティです。
というのも、「食べる」という行為は誰がするのか注目すると、「わたし」だということが分かります。
そして、この行為は未完了であることもポイントです。
例えば「わたし」→「小千田」にしてみましょう。
この文で「食べる」という行為をするのは「小千田」であるので、話し手の意志は関係なくなってしまうので、意志のモダリティにはなりません。
基本的に言いきりの形は断定のモダリティと解釈されることが多いのですが、
・行為の動作主が話し手である
・その行為は未完了である
この条件が揃う時、意志のモダリティとなります。
ちなみに、断定のモダリティと同じように(Φ)で表されます。
札幌に行くのは話し手である「僕」です。
また、まだ札幌に辿り着いていないので、動作は未完了です。
よって、意志のモダリティ(Φ)になります。
この「書こう」は意志のモダリティになります。
「書こう」などの「○○しよう」といった形をとる動詞は意向系と呼ばれますが、典型的な意志のモダリティと言えます。

コメントを残す